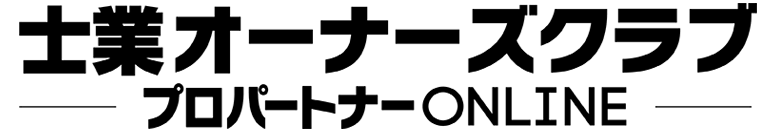2023.09.25
インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応に関するお知らせ
2023年10月01日(日)より、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されますので、弊社の同制度への対応についてお知せいたします。
弊社ではインボイス制度の対象となる課税取引のご利用について、
2023 年10月以降の決済分より、同制度の要件に対応できるようにいたします。
【当行適格請求書発行事業者登録番号のご案内】
株式会社アックスコンサルティングの登録番号をご案内いたします。
適格請求書発行事業者登録番号
T9011001004344