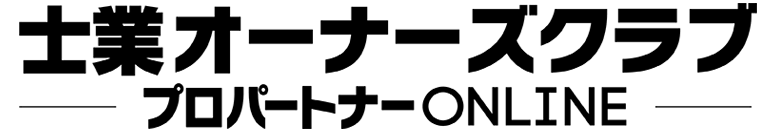- TOP
- 検索結果
検索結果(全2件)
フィルタ
並べ替え
2020.11.24