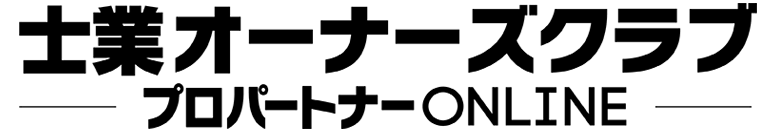顧客と職員に選ばれる成長事務所の人事制度とは?士業事務所の 給与・評価を徹底解説!
- 2022.02.17
- プロパートナーONLINE 編集部
今回のテーマは『士業事務所の人事評価制度設計の基本』。
人事領域のコンサルティングを数多く手がける
社会保険労務士法人ビルドゥミー・コンサルティング代表の望月建吾先生が解説します。
従業員に支払いたい年収額に応じた報酬単価、
賃金バンドに込めたメッセー ジ、
何を可視化するのかの決定です。
一つ目の単価設定は非常に重要です。
まず、みなさんは顧客に提供しているサービスの価格をどのように設定していますか?
同業他社の価格をリサーチして、
同等・もしくは単価を落とした設定にしているケースがあるかもしれません。
しかし、他社水準に引っ張られすぎると、
必要工数に対する単価の考え方が破綻し、
従業員に支払いたい年収額を捻出できなくなるほか、
十分な役員報酬を確保できない、
やってもやっても法人利益が残らないなどの悪循環なリスクを孕んでしまいます。
なぜなら、他社の水準が適正報酬額であると言い切れないためです。
解決のポイントとしては、法人利益として確保しておきたい適正な利益率を決めて、
予めその額を捻出する想定で人件費率の適正割合を設定すること。
他社のサービス価格を水準にするのではなく、
従業員に支払いたい年収額から逆算して、担当者のレベルに応じた単価を決めることです。
例えば、売上に対する理想の割合は、営業利益10%以上、実務担当者人件費率が34%、
営業マン、間接営業部門の人件費が各8%、事務所の賃料、
そのほか諸経費で20%ほどという具合に、です。
また、実務担当者の時間当たりの業務単価を正確に算出しておくことも重要です。
これをしない限り、業務改善の成果が曖昧になるので必ず算出しておくようにしましょう。
次に、賃金バンドの長さです。
これは、〝どのグレードに長く滞留してほしいか〞
という事務所代表のメッセージでもあります。
つまり、各等級の賃金バンドの長さやほかの等級と重なる部分が、
従業員に支払いたい年収額や従業員の昇格イメージと合致しているかということです。
例えば、新卒からの3年間は一人前に育つ修行期間だから、その等級には3年であるとか、
次の等級はより上位の等級のため4年程度で昇格してもらいたい
といったメッセージを込めたバンドにするのです。
また、人事制度・賃金制度の「何を」可視化するのかをよく考えて決めてください。
評価の基準なのか、処遇のしくみなのか、評価のルールなのか。
もしかしたら、従業員の望む可視化とは違ったものになるかもしれません。
これは他社を真似てもいいとは限りません。代表の先生がよく考えて決めてください。
制度設計の前にまずは、提供するサービス報酬額の利益割合を決めることが重要です。

・提供しているサービス価格の設定を今一度見直してみる
・他社水準に引っ張られすぎると従業員に支払いたい年収を捻出できなくなる恐れも...
・入社した従業員をどのくらいの期間でプロモーションしていくか設定しておくこと
・給与と評価は腹落ちすることが大切!各等級の役割責任の基準など可視化させておこう

人事領域のコンサルティングを数多く手がける
社会保険労務士法人ビルドゥミー・コンサルティング代表の望月建吾先生が解説します。
「他社水準」ではなく 自社の適正報酬単価を
士業事務所の人事制度・賃金制度設計で重要なポイントは3つ。従業員に支払いたい年収額に応じた報酬単価、
賃金バンドに込めたメッセー ジ、
何を可視化するのかの決定です。
一つ目の単価設定は非常に重要です。
まず、みなさんは顧客に提供しているサービスの価格をどのように設定していますか?
同業他社の価格をリサーチして、
同等・もしくは単価を落とした設定にしているケースがあるかもしれません。
しかし、他社水準に引っ張られすぎると、
必要工数に対する単価の考え方が破綻し、
従業員に支払いたい年収額を捻出できなくなるほか、
十分な役員報酬を確保できない、
やってもやっても法人利益が残らないなどの悪循環なリスクを孕んでしまいます。
なぜなら、他社の水準が適正報酬額であると言い切れないためです。
解決のポイントとしては、法人利益として確保しておきたい適正な利益率を決めて、
予めその額を捻出する想定で人件費率の適正割合を設定すること。
他社のサービス価格を水準にするのではなく、
従業員に支払いたい年収額から逆算して、担当者のレベルに応じた単価を決めることです。
例えば、売上に対する理想の割合は、営業利益10%以上、実務担当者人件費率が34%、
営業マン、間接営業部門の人件費が各8%、事務所の賃料、
そのほか諸経費で20%ほどという具合に、です。
また、実務担当者の時間当たりの業務単価を正確に算出しておくことも重要です。
これをしない限り、業務改善の成果が曖昧になるので必ず算出しておくようにしましょう。
次に、賃金バンドの長さです。
これは、〝どのグレードに長く滞留してほしいか〞
という事務所代表のメッセージでもあります。
つまり、各等級の賃金バンドの長さやほかの等級と重なる部分が、
従業員に支払いたい年収額や従業員の昇格イメージと合致しているかということです。
例えば、新卒からの3年間は一人前に育つ修行期間だから、その等級には3年であるとか、
次の等級はより上位の等級のため4年程度で昇格してもらいたい
といったメッセージを込めたバンドにするのです。
また、人事制度・賃金制度の「何を」可視化するのかをよく考えて決めてください。
評価の基準なのか、処遇のしくみなのか、評価のルールなのか。
もしかしたら、従業員の望む可視化とは違ったものになるかもしれません。
これは他社を真似てもいいとは限りません。代表の先生がよく考えて決めてください。
制度設計の前にまずは、提供するサービス報酬額の利益割合を決めることが重要です。

・提供しているサービス価格の設定を今一度見直してみる
・他社水準に引っ張られすぎると従業員に支払いたい年収を捻出できなくなる恐れも...
・入社した従業員をどのくらいの期間でプロモーションしていくか設定しておくこと
・給与と評価は腹落ちすることが大切!各等級の役割責任の基準など可視化させておこう

プロフィール

望月 建吾氏
社会保険労務士法人ビルドゥミー・コンサルティング 代表社員
特定社会保険労務士/残業ゼロ将軍。2010年に開業し、残業ゼロの労務管理実績300社以上、人事制度づくり支援実績300社以上。書籍『社労士・弁護士の労働トラブル解決物語』 シリーズ、『「人事・労務」の実務がまるごとわかる本』など多数出版。TVなどのメディアに出演など多岐にわたって活躍している。
特定社会保険労務士/残業ゼロ将軍。2010年に開業し、残業ゼロの労務管理実績300社以上、人事制度づくり支援実績300社以上。書籍『社労士・弁護士の労働トラブル解決物語』 シリーズ、『「人事・労務」の実務がまるごとわかる本』など多数出版。TVなどのメディアに出演など多岐にわたって活躍している。
関連コンテンツ