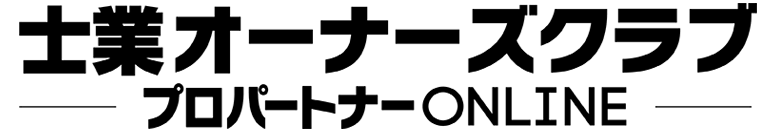事務所の生産性と利益率は「所長の在り方」で決まる。生産性と利益率向上のために所長が「やってはいけないこと」とは?
- 2023.03.02
- プロパートナーONLINE 編集部

「『部下のパフォーマンスが低い』『事務所の生産性や利益率が低い』
という悩みを抱えている場合、それは所長の“在り方”に原因があることが多いのです」。
一般社団法人日本経営心理士協会・代表理事の藤田耕司氏はそう話します。
その根拠となるのが「情動伝染」「同調性」「一貫性」という人間の性質。
そこで、事務所の生産性や利益率を上げるうえで重要な“所長の在り方”を、
藤田氏が解説します。
経営心理士とは
人間心理に基づいて、人を育て、組織を拡大させ、
業績を伸ばす指導ができるようになるための専門資格。
1,200件超の経営改善事例から作成された実践的なカリキュラムで、
これまでのべ7,000名を超える士業、経営者が経営心理士講座を受講している。
その成果の高さから、講座の内容は金融庁や日本銀行、士業の認定研修にも導入されている。
経営心理士講座: https://keiei-shinri.or.jp/
人間心理に基づいて、人を育て、組織を拡大させ、
業績を伸ばす指導ができるようになるための専門資格。
1,200件超の経営改善事例から作成された実践的なカリキュラムで、
これまでのべ7,000名を超える士業、経営者が経営心理士講座を受講している。
その成果の高さから、講座の内容は金融庁や日本銀行、士業の認定研修にも導入されている。
経営心理士講座: https://keiei-shinri.or.jp/
感情がコントロールできない所長は生産性を下げる
無意識の「独り言」にも要注意!
経営心理士講座を受講している経営者から、「職員のパフォーマンスや生産性を上げるには、どうしたらいいでしょうか?」
と聞かれることがよくあります。
職員のパフォーマンスや生産性を上げたいのであれば、
はじめに考えるべきことは
「パフォーマンスや生産性を下げる要因」を排除することです。
では、職員のパフォーマンスや生産性を下げている要因は何か?
その一つが、所長(上司)の感情の状態です。
所長(上司)の感情の状態が悪いと、部下は質問しづらくなります。
上司に聞けば5分で終わる仕事なのに、
質問しづらいことが原因で質問のタイミングをうかがう、
どうにか自力で調べるなどして、1時間かかってしまうとします。
これにより55分の非効率が生まれます。
こういったことを部下が毎日のようにやっていたとしたら、
相当な非効率が生まれていることになります。
こうして部下のパフォーマンスや生産性が大きく下がり、
その結果、事務所の生産性や利益率も下がります。
でも、多くの上司はそういう状況にあることに気づいていません。
また、所長の感情は職員に伝染します。
たとえば、所長がイライラした状態で事務所にいると、
事務所全体がピリピリした空気になります。
逆に、所長の機嫌が良ければ、職員もリラックスした雰囲気になります。
このように感情は人から人へ伝染するという性質を持ちます。
これを心理学では「情動伝染」といいます。
特に、立場が上の人の感情は、
立場が下の人により強く伝染しやすいという性質を持ちます。
つまり組織では、川上にいる上司から、川下の部下へと感情が流れます。
そのため、上司の感情の状態が悪いと、
部下たちの感情に大きな悪影響を与えます。
その状況で仕事をしているとモチベーションや集中力が下がり、
「不安で集中できない」「事務所に行くのがつらい」といった状況になり、
パフォーマンスや生産性が下がるだけではなく、離職にもつながりかねません。
ですから、感情の流れの最も川上に位置する所長は、
自分の感情を良い状態に保つことも重要な仕事なのです。

部下の感情に影響を与えるものとして意外と見落としているのが、独り言です。
上司の独り言は、本人が思っている以上に部下は聞いていますし、気にしています。
たとえば、上司がパソコンを見ながら「最悪だな」とか
「なんだよこれ」とか言っているとします。
それは社外の人から来たメールに対して発した独り言だったとしても、
部下は誰に向けて言っているのかわかりません。
「もしかして自分のこと?」と不安になる部下もいます。
こういった独り言が部下の集中力を下げ、ストレスを高めます。
さらに、その独り言の声が大きいと、部下は自分たちに言っているのか、
ただ声が大きいだけなのかがわからず、
「話しかけるべきか、放っておくべきか」という迷いも生じます。
ほかにも、負の感情を発している例としては、
キーボードを打つ音なども挙げられます。
イライラしているときにキーボードを打つ音が大きくなってしまう人なども要注意です。
このように感情のコントロールができない所長や上司は、
職員のパフォーマンスや事務所の生産性を下げ、
さらには離職の要因もつくっているのです。
事務所の生産性と利益率を上げる所長&上司の在り方
●自分の感情が周囲に影響を与えているという自覚を持つ
●独り言などで思いがけず負の影響を与えていないか省みる
●自分の感情が周囲に影響を与えているという自覚を持つ
●独り言などで思いがけず負の影響を与えていないか省みる
所長の在り方が言葉に力を与える
まずは自分が率先して理念やビジョンを体現する
人間の習性として、同調性というものがあります。集団のなかで大勢の人がやっていること、
影響力の強い人がやっていることを真似するという習性です。
士業事務所で影響力が強い人といえば所長です。
そのため、所長の在り方はそのまま部下が真似をする可能性が高いということです。
たとえば、所長が感情の状態が悪いことが多く、
質問しづらい雰囲気をつくり、部下の質問に答えることをしないと、
そういう環境で育った職員も部下への指導を積極的にやろうとはしなくなります。
そして、自分の仕事が忙しいと質問しづらい雰囲気をつくり、部下の生産性を下げます。

また、所長がネガティブな独り言を頻繁に言ったり、
キーボードの打ち方などの振る舞いが荒っぽかったりすると、
部下も同じことをやる可能性が高くなります。
所長のみならず、マネージャーやベテラン職員までそういったことをやるようになると、
部下はますます仕事がしづらくなります。
その結果、事務所の生産性や利益率はさらに下がり、離職率が上がります。
そのため、所長の在り方を職員も真似をする傾向にあることを自覚したうえで、
事務所の生産性や利益率を上げるような在り方を普段から意識することが重要になります。
事務所の生産性と利益率を上げる所長&上司の在り方
●職員は所長の在り方を真似る傾向がある
●生産性と利益率を上げる在り方を普段から意識する。
●職員は所長の在り方を真似る傾向がある
●生産性と利益率を上げる在り方を普段から意識する。
職員を動かすには「理由」に納得してもらうこと
そして、諦めずに粘り強く言い続けることが大切
昨今はDXに取り組む企業も増えており、会計事務所にもDXの波が押し寄せています。特に、会計事務所向けにはさまざまな自動化ツールが開発されていて、
そういったツールを導入し、業務効率を格段に上げている事務所もあります。
DXに取り組めるかどうかは、今後の会計事務所の生産性や利益率を大きく左右します。
しかし、職員にもそういった意識がなければ、新たなツールを導入しても、
これまでのやり方を変えようとはせず、ツールを使うこともありません。
そのためDXは、ただツールを導入すればいいというわけではなく、
職員の意識改革から始める必要があります。
この意識改革に成功するかどうかが、
事務所の将来性を左右するといっても過言ではないでしょう。
その意識改革を進めるにあたっては、まず理由を話し、納得を得ることです。
人は「理由」を大事にする生き物です。
指示や提案を受けた際、理由に納得できるとそれに応じようとします。
「なぜ新たなツールを導入しなければいけないのか」を
事務所の現状や今後の展望に基づいて話したうえで、
「だからやり方を変えてほしい」と伝えるのと、
ただ「やり方を変えてほしい」と伝えるのでは、
相手が応じてくれる確率は大きく異なります。
そして何より、“諦めないこと”です。
新たな方針を導入し、はじめは「この方針でいくぞ」と言っていても、
しばらく経つと何も言わなくなる。
その結果、その方針は形骸化する。
こういった「言っては諦め、形骸化する…」を繰り返すと、
何か新たな方針を示しても、職員は「どうせまた何も言わなくなる。
今のうちだけだから無視しておこう」と思うようになり、統率がとれなくなります。
そのため、やると決めたら最後までやり切る覚悟で進めることが重要です。
諦めずに繰り返し伝え、
「所長がこれだけ言っているから、もうやるしかない」
と職員が根負けするぐらい言い続ける。
それにより職員の行動が変化すると、
「この人は言ったらやり切る人だ」と職員から思われるようになります。
この「一貫性」が統率力を高めます。
こういった所長の在り方がDXを推進し、
ひいては事務所の生産性や利益率を上げることになります。
士業事務所は小規模なところが多いため、
所長本人が思っているより、所長の影響は大きいものです。
だからこそ、事務所の生産性や利益率を上げるには、
そのために必要な在り方を所長が継続的に体現していくことが大切です。
事務所の生産性と利益率を上げる所長&上司の在り方
●指示や提案をする際は、理由をきちんと伝える
●決めた方針は職員が根負けするぐらい一貫して言い続ける
●指示や提案をする際は、理由をきちんと伝える
●決めた方針は職員が根負けするぐらい一貫して言い続ける

まとめ 事務所の生産性と利益率を上げる所長&上司の在り方
- 自分の感情が周囲に影響を与えているという自覚を持つ
- 独り言などで思いがけず負の影響を与えていないか省みる
- 他の職員は所長の在り方を真似る傾向がある
- 生産性と利益率を上げる在り方を普段から意識する
- 指示や提案をする際は、理由をきちんと伝える
- 決めた方針は職員が根負けするぐらい一貫して言い続ける
プロフィール

藤田耕司氏
一般社団法人日本経営心理士協会 代表理事
FSG税理士事務所 代表税理士
大手監査法人を経て、2012年にFSG税理士事務所を設立。
2015年に一般社団法人日本経営心理士協会を設立し、
人間心理に基づいて経営改善を行うための経営心理士講座を開催。
全国からのべ7,000名を超える士業、経営者が講座を受講。
その成果の高さが認められ、講座の内容は金融庁や日本銀行でも導入される。
日経新聞や週刊ダイヤモンド、東洋経済、PRESIDENTはじめ、
数多くのビジネス媒体からも取材を受ける。
https://keiei-shinri.or.jp/
FSG税理士事務所 代表税理士
大手監査法人を経て、2012年にFSG税理士事務所を設立。
2015年に一般社団法人日本経営心理士協会を設立し、
人間心理に基づいて経営改善を行うための経営心理士講座を開催。
全国からのべ7,000名を超える士業、経営者が講座を受講。
その成果の高さが認められ、講座の内容は金融庁や日本銀行でも導入される。
日経新聞や週刊ダイヤモンド、東洋経済、PRESIDENTはじめ、
数多くのビジネス媒体からも取材を受ける。
https://keiei-shinri.or.jp/
関連コンテンツ