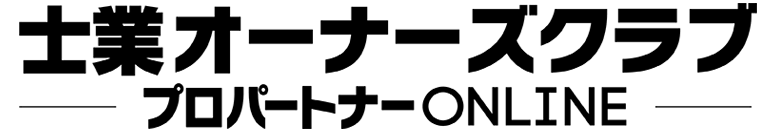未経験の職員が3カ月で即戦力に! 徹底した仕組み化で年間80件の相続案件獲得を実現
- 2022.01.13
- プロパートナーONLINE 編集部

2020年7月に開業し、現在4名のスタッフで年間80件の相続案件を受託している島根税理士事務所。
独立以来、目標である年間100件の継続的な受注を目指し、
士業との連携や社内体制の構築に着手します。代表の島根 猛氏がその秘訣を公開!
相続案件に絞って受託し、その他案件は連携先へ
私たちの事務所は、主に相続に関わるあらゆる業務をワンストップで対応しています。顧問業務に関しては、基本的に受託しないのですが、金融機関や他士業の先生からの紹介で、
将来的に相続や事業承継の案件に発展しそうであれば、受けることもあります。
ただ、その場合はお客様に会計データを用意していただくことを条件にしていて、
こちらで記帳業務は行いません。このようなルールを設定することで、
顧問業務にかける時間をコントロールし、相続案件に対応する時間を捻出しています。
当社は相続業務に特化し、それ以外の戸籍謄本の取り寄せ、
金融機関の残高証明発行などの手続き業務に関しては、
提携先の行政書士や司法書士の先生に対応してもらい、
チームで仕事を回すようにしています。
連携を取りながら、それぞれが得意分野を担当していけば、お互いにスムーズですし、
生産性も向上していきます。この1年間は、特に士業の先生たちとの関係構築に力を注ぎ、
現在は大手司法書士法人から月に3~4件の紹介を受けています。
また、ほかの税理士や会計士の先生のお手伝いも5件ほどさせていただきました。
「相続業務はあまり得意ではないけれど、お客様との結びつきが強い」という先生は、
当社が実務を代行することで、お客様の信頼関係を損なわずに相続案件の受諾ができます。
一方、私たちは相続案件を受任できるため、
お互いにメリットのある関係性が構築できていると思っています。
また、お付き合いのある金融機関からの紹介が月4~5件。
不動産会社から自宅売買後の確定申告手続きが数件と、
以前担当したお客様からの二次相続の依頼や身内の相続相談が年5件ほどあります。
これらの案件を受任できたのは、コロナ禍であっても営業活動を続けてきたからです。
直接の訪問は難しいため、今年はニュースレターやはがきを送ったり、
電話のついでにお話をさせていただいたりといった活動が中心でした。
以前、相続案件をお手伝いしたお客様にも必ず年に1回はニュースレターを送るなどして、
関係維持に努めています。相続案件の受任は、
お客様との関係性を深めていくことが重要なので、
これから積極的に案件を取っていきたいという先生は、
まずはDMを送るなど、自らアプローチをして距離感を縮めていくことをおすすめします。
業務工程を見直すことで、スタッフの育成にも成功
営業活動に付随して、効率的に業務をこなすために社内体制の再構築を考える必要がありました。現在、事務所では私が契約を行い、資料をお預かりして、
準確定申告の書類をつくりますが、それ以外の計算ソフトへの入力や
財産評価などは一次や二次のチェックも含めてスタッフに任せています。
私が行うのは、最終チェックです。今年の4月からこのように業務フローを改善し、
仕組み化することによって、私が受け持つ業務を減らしました。
本来、私は人に任せることが得意ではなく、
自分でやったほうが正確で早いと思っていました。
しかし、思い切って任せてみたところ、スタッフも成長し、
案件をたくさん受注しても上手く回せるようになりました。
また、自分の手が空くわけですから、
その分、新規案件の獲得にも動けるというメリットもあります。

徹底した業務管理と教育がプラスの相乗効果を生む
受任案件が増えるに伴い、案件管理についての課題も出てきます。私たちの事務所ではMykomonで相続業務の進捗管理をしており、
さらに1週間に1〜2回は進捗会議を行いながら、抜け漏れを確認。
また、Chatworkで各担当者の行うToDoリストを全員が共有できるようにもしています。
誰が今何をしているか把握することは、業務効率化の面でも大切なポイントです。
スタッフの育成はOJTが中心で、
初期段階で作業をしながら相続業務の大枠を掴んでもらっています。
いきなり一から十まで覚えるのは難しいので、制度の理解も含めて、まずは3カ月間、
徹底的に相続税の基礎を学んでもらいます。4カ月目からは細かい仕事も覚えてもらい、
OJTでは伝えきれない部分などは外部研修に頼ることもあります。
最初は戸惑うと思いますが、基本的に当社は相続税しか扱わないため、
スタッフの成長スピードはかなり早いと思います。
実際に相続の知識・経験がゼロの状態で入社したスタッフが、
半年で完璧な申告書を作成できるレベルに成長しました。
一つ何かができるようになると自信がつくので、
まずは経験を積み、自信を養っていくことが大切です。
業務の生産性を上げるためには、スタッフの成長が欠かせません。
スタッフが育つことで事務所も発展していきますし、
良い相乗効果を発揮できるはずです。
2020年7月に事務所を立ち上げてから現在まで、
お客様の数が増えた背景には、
こうしたスタッフとの信頼関係構築も大きな要因としてあります。
未経験のスタッフが時折立ち止まってしまうように、私もいまだに悩みながら、
失敗ながら、まさに「トライアル・アンド・エラー」を繰り返しています。
新しいことにチャレンジする時は、「一歩一歩前向きに、成長を急がない」
ということを自分にも言い聞かせながら、
未経験から相続業務に挑戦するスタッフと向き合っているつもりです。
言うならば、横付きで子供の育つ過程を見守り、
お互いに成長を喜ぶ感覚にも近いかもしれません。
私もスタッフの成長に関しては、ついつい熱くなってしまうのですが、
日々少しずつでも前進してくれる姿を見ると、本当に嬉しくなるものです。
【職員の声】
マニュアル活用で、相続は「特別な業務ではない」と実感
相続業務は、スタッフが直接関わることがめったになく、難易度も高いため、税理士の方にとっても“特別な業務”というイメージでした。
最初は、「本当に3カ月で相続業務ができるようになるのか」
という不安もありましたが、マニュアル通りに進めることで、
未経験からでも一連の財産評価業務ができるようになります。
また、島根先生や先輩方から丁寧に順を追って教えていただくことで、
短期間でも基本的な評価業務を覚えられましたし、
より理解を深めるために相続税や土地評価に関する本を読み、
専門用語や特例・全体像を把握できるように努力しようという向上心も湧いてきます。
当事務所のマニュアルには、お客様に対するきめ細やかな気配りのコツや、
全体を俯瞰してプロとして対応できるようになるポイントが無駄なくまとめられています。
作業環境についても、PC機器やソフトなども非常に操作性が良く、
初心者でも使いやすいですし、短期間でも作業手順を覚えられます。
一方で、分からないことはスルーせず、先生や先輩のアドバイスを受けながら
継続的にノートにまとめて知識を定着させることも重要だと感じています。
例えば、土地評価の際に使用するソフトの操作では、
「何をどう計測するか」という業務の意義を理解することはもちろん、
最初のうちは操作への慣れも必要です。セットバックなどの個別事情は、
経験を重ねるうちに徐々に理解が深まってきていると実感していますし、
入力の際のルールをしっかり定着させることが、
チェックをする際にも重要だということが分かりました。
作業内容を理解するだけでなく、
誰が見ても同じクオリティーにまで仕上げることは簡単なようで難しいものです。
マニュアルを理解しながら、4カ月以降も基本を怠らず、
作業と知識を同時により定着させていくことが大切だと考えています。
相続業務体制強化のポイント
- 他士業との連携による役割分担で得意分野を回し合う関係性を構築
- 業務フローの改善と業務管理で作業効率と受注件数が増加
- 業務を相続税に絞ることでスタッフの成長スピードがアップ
島根氏の相続業務ノウハウをマニュアル化!
「相続業務を効率化したい」「相続業務に対応できる職員を育てたい」
「相続チームの教育体制を整えたい」
という事務所は必見!
島根氏が培ってきた相続申告業務のノウハウがギュッと詰まっています。
詳細はこちらから!

プロフィール

島根猛氏
島根税理士事務所 代表
保険会社の営業職を経て、税理士法人に勤務し、数多くの資産税案件に携わる。
2020年に開業後は、顧客のニーズに沿ったオーダーメードの相続対策の提案を強みに、ワンストップで対応。
営業から実務までのノウハウをまとめた『相続基本実務MANUAL』が好評発売中。
保険会社の営業職を経て、税理士法人に勤務し、数多くの資産税案件に携わる。
2020年に開業後は、顧客のニーズに沿ったオーダーメードの相続対策の提案を強みに、ワンストップで対応。
営業から実務までのノウハウをまとめた『相続基本実務MANUAL』が好評発売中。
関連コンテンツ