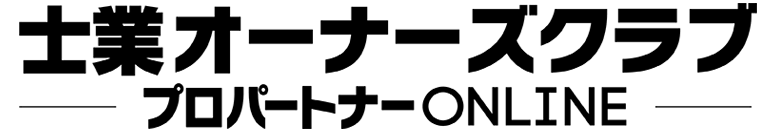民事信託を活用し2年間で200件の相続案件獲得!あすか税理士法人
- 2020.05.26
- 株式会社 アックスコンサルティング

2015年1月からの相続税改正で、 相続対策の重要性が高まり、相続マーケットは広がりを見せています。
税理士にとって追い風でもありますが、流れに乗って相続ビジネスを拡大している例は、さほど多くありません。
そんな中、 相続案件獲得の新手法として注目されるのが 「民事信託」。
どのようにして相続ビジネス拡大に活用すればいいのでしょうか。
「争族」「認知症」の増加で相続問題解決の難易度が上昇
相続税基礎控除額引き下げで、相続税を支払う対象者が増加し、相続対策のニーズが高まりました。税理士にとってビジネスチャンスが拡大した一方で、その追い風に乗り切れていないケースも少なくありません。
その背景には、近年、相続問題解決の難易度が上昇していることが挙げられます。
まず考えられるのは「争族」の増加です。
2ページのグラフ1~3を見ていただくとわかるように、遺産分割事件は増加傾向にあり、「争族」は多額の遺産がある大家族の話ではなく、分割できない少額資産を少人数で争う出来事だということが読み取れます。
現在はテレビ番組やインターネット等で相続問題に関する情報が大量にあふれ、各人の権利意識が高まっていることも、遺産分割事件増加に影響を与えています。
もうひとつは、相続財産における不動産の割合が依然と高いことが考えられます。
グラフ4は相続財産のうち、不動産が占める割合を示します。
バブル崩壊時には80%に上り、そこからダウン傾向にあるものの、依然と高い比重を占めることには変わりありません。
不動産は分割が難しい財産です。
自宅等の不動産以外、相続財産がない場合、遺産分割は困難になり、やむなく複数の相続人が共有するという事態に陥ることもあるでしょう。
さらに近年の相続問題解決を困難にしているのは、認知症患者の増加です。
グラフ5を見る通り、認知症患者は増加の一途をたどっています。
認知症になってしまうと、意思表示ができないので、相続対策がほぼ絶望的になります。
このような難易度が高まった相続問題を解決する手段として、民事信託が注目を浴びています。
- 認知症対策
- 共有持分対策
- 遺留分対策
- 事業組成
- 法人化対策
- 自社株対策

なぜ民事信託を活用する専門家が少ないのか?
民事信託とは、贈与税が発生しないで、不動産や金融資産の名義を信頼できる人に託し、託されている人が、運用や処分等を行う制度。専門家はもちろん、相続予備軍とその家族の間で高い関心を集めています。
一方、現時点では民事信託を活用して相続案件を獲得している例が多くないのが現状です。
なぜ、民事信託を活用する専門家が少ないのでしょうか。
大きな理由は、民事信託の仕組み自体がわかりづらい点にあります。
適用を間違うと思わぬ税金が発生したり、意図していないような財産承継が行われてしまうリスクが横たわっています。
まだまだ税理士等の専門家にとって未開拓の分野ともいえるでしょう。
もうひとつの理由は、「民事信託は節税にならない」「節税にならないので、どこで報酬を得ればいいのかわからない」という先入観が一部の税理士等に根強いことにあります。
こうした思い込みが、民事信託の普及にブレーキをかけていると推測されます。
「民事信託」を活用し2年間で200件の相続案件獲得
実際に民事信託を活用し、相続ビジネスを拡大している事例を紹介します。あすか税理士法人(北海道札幌市)は民事信託をフックとして、2年間で約200件の相続案件を獲得しました。
最近は「民事信託」を切り口にハウスメーカーや生命保険会社等とタイアップして、無料相談、案件獲得へとつなげています。
代表社員税理士で法学博士の川股修二氏は「タイアップするには、業務との親和性をアピールすることが大切です」と語ります。
たとえば、ハウスメーカーの場合、次のように、お客様の認知症で契約が中断した苦い経験を持つといいます。
- 建設の打ち合わせが終了し、いざ契約というときに、施主さんが急病で意識不明になった
- 有持分の土地の有効活用の提案中に、持分権者のひとりが認知症になった
- 施主である夫の配偶者が認知症になった
そんな問題を「民事信託で解決できます」と、業務との親和性をアピールしてセミナーを提案すれば、話がスムーズに進むといいます。
民事信託報酬獲得3つのポイント
「民事信託は節税にならない」「節税にならないので、どこで収益を得ればいいのかわからない」という声について、川股氏は次のように返答しています。「民事信託行為では不動産取得税が、ほぼかからなくなります。ここが重要です。登録免許税も1/10になるので、不動産を動かす際には便利です」(川股氏)
民事信託の報酬に関しては、あすか税理士法人の事例を下に記してあります。

不動産所得を有する医業を営む個人が、不動産事業の法人化を希望。
所有不動産が陳腐化していたことから、大規模な建て替えの必要が生じていた事例です。
不動産事業の法人成りスキームで民事信託を活用し、図にあるような報酬を得られました。
ポイント1. 周辺業務のコンサルフィーで高額報酬を獲得
報酬を民事信託単体で考えるのではなく、その周辺業務のコンサルフィーを含めた全体で考えることが重要。この場合、不動産流通税節税と消費税還付スキームの報酬が合計で500万円に上り、高額報酬を実現しています。
ポイント2.継続報酬を得る
民事信託を契約すると、信託期間中は毎年、民事信託税務会計を実施する必要があります。この報酬が年間90万円。
一般的な法人顧問料よりも高額な点が特筆に値します。
ポイント3.ハウスメーカーからの紹介料を得られる
不動産の建て替えが生じる場合、ハウスメーカーからの紹介料が期待できます。この事例では、報酬対象取引総額が約24億円に上ることから、料率が1~3%でも、報酬が約3,400万円に達しました。
このように、民事信託をフックにすると、相続ビジネス全体の報酬アップを実現することを、あすか税理士法人の事例が示しています。
従来型の相続ビジネスとは違うキャッシュポイントが生まれるのです。

 あすか税理士法人
あすか税理士法人代表社員 税理士 法学博士
川股 修二 (かわまた しゅうじ)氏
北海道大学大学院法学研究科博士後期課程(租税法専攻)修了博士(法学)。北海学園大学法科大学院、札幌大学大学院法学研究科、札幌学院大学法学部 客員教授。第38回 日税研究賞奨励賞受賞。3年で組織を倍増(17名から34名)、北海道で4拠点を展開。6カ月で新規売上7,000万円増を達成。2年間で200件の資産税案件を獲得。
関連コンテンツ